生命保険を契約する際に気になるのが、「保険金の受取人を誰にするか」です。一般的には配偶者や子どもが受取人に指定されることが多いですが、「孫を受取人にできるのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。
今回は、孫が生命保険の受取人になれるのか、どんな条件があるのか、そして税金の影響について詳しく解説します。
1. 保険金の受取人の基本ルール
生命保険の受取人は、契約者が自由に指定できるわけではなく、一定のルールが設けられています。
受取人になれる範囲
生命保険の受取人として指定できるのは、基本的に配偶者や2親等以内の血族です。
2親等には、子ども、孫、両親、兄弟姉妹が含まれます。そのため、孫も理論上は生命保険の受取人として指定することが可能です。
ただし注意点がある!
孫を受取人にする場合、税金の負担が大きくなることがあるため、慎重に検討する必要があります。この点については後ほど詳しく解説します。
2. 孫が保険金を受け取る主なケース
孫が生命保険の受取人になるのは、以下のようなケースが考えられます。
(1) 保険契約で孫を受取人に指定した場合
契約者が意図的に孫を受取人として指定すれば、孫が保険金を受け取ることができます。
「孫の教育資金として使ってほしい」といった理由で、孫を受取人にするケースが考えられます。
(2) 代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生した場合
代襲相続とは、本来相続人であるはずの子ども(被保険者の子)が先に亡くなっている場合、その子ども(被保険者の孫)が相続人となる仕組みです。
この場合、孫が法定相続人になるため、保険金を受け取る可能性があります。
3. 孫が受け取る場合の税金はどうなる?
生命保険金には、受取人の立場によって課税される税金が異なります。孫が受け取る場合、特に注意が必要です。
相続税が課税される
孫が生命保険金を受け取ると、多くの場合相続税の対象になります。
相続税には非課税枠があり、
👉 法定相続人1人あたり500万円までが非課税です。
ただし、孫は法定相続人に含まれない場合も多く、非課税枠を利用できないケースがあるため注意が必要です。
「一代飛ばし」の税負担
孫が保険金を受け取る場合、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
これは、「一代飛ばし」と呼ばれる税制上の考え方によるもので、通常よりも20%加算された税率が適用されることがあります。
📌 例:孫が3,000万円の保険金を受け取る場合
- 本来の相続税率が30%なら、36%(+20%加算)が適用される
- 結果として、3,000万円 × 36% = 1,080万円の相続税がかかる
このように、孫を受取人にすると税負担が大きくなるため、税理士などの専門家に相談しながら検討することが重要です。
4. 孫を受取人にする際のポイントと注意点
孫を生命保険の受取人にする際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
✅ 受取人指定は契約時にしっかり明記
「孫」とだけ書くのではなく、孫の名前と続柄を明確に記載しましょう。
曖昧な表現だと、万が一のときにトラブルになる可能性があります。
✅ 相続税・贈与税を考慮する
孫が受け取る場合、相続税の優遇が少ないため、税負担を考えた受取額の設定が重要です。
相続税対策として、配偶者や子どもと分散して保険金を設定するのも一つの方法です。
✅ 受取人の変更は可能
一度指定した受取人は、契約後も変更することが可能です。
「孫が生まれた」「教育資金を準備したい」などのタイミングで、見直しを検討しましょう。
5. 保険金請求の流れと必要書類
孫が保険金を受け取ることになった場合、スムーズに手続きを進めるために、必要な書類を事前に準備しておくと安心です。
📌 必要書類一覧
✅ 死亡診断書(被保険者が亡くなったことを証明)
✅ 保険証券(契約内容を確認)
✅ 受取人の身分証明書(免許証・パスポートなど)
✅ 戸籍謄本や住民票(法定相続人の確認)
📌 ポイント!
- 戸籍謄本の取得に時間がかかる場合があるため、事前に手続きを進めておくとスムーズ。
- 保険金の請求期限は3年。早めに手続きを進めるのがベスト。
まとめ:孫を受取人にするなら慎重に計画を!
孫を生命保険の受取人に指定することは可能ですが、相続税や税負担を考慮した計画が必要です。
✔️ 孫が受け取る場合のポイント
✅ 受取人指定を明確にする
✅ 相続税・贈与税の影響を把握する
✅ 必要に応じて専門家に相談する
「孫に資産を残したい!」と考えている方は、保険の見直しや相続対策をしっかり行い、後々のトラブルを防ぎましょう。
💡 保険や相続に関するご相談は専門家へ!
適切なプランを立てることで、安心して家族に資産を残すことができます。
ぜひ、保険の見直しを検討してみてくださいね!

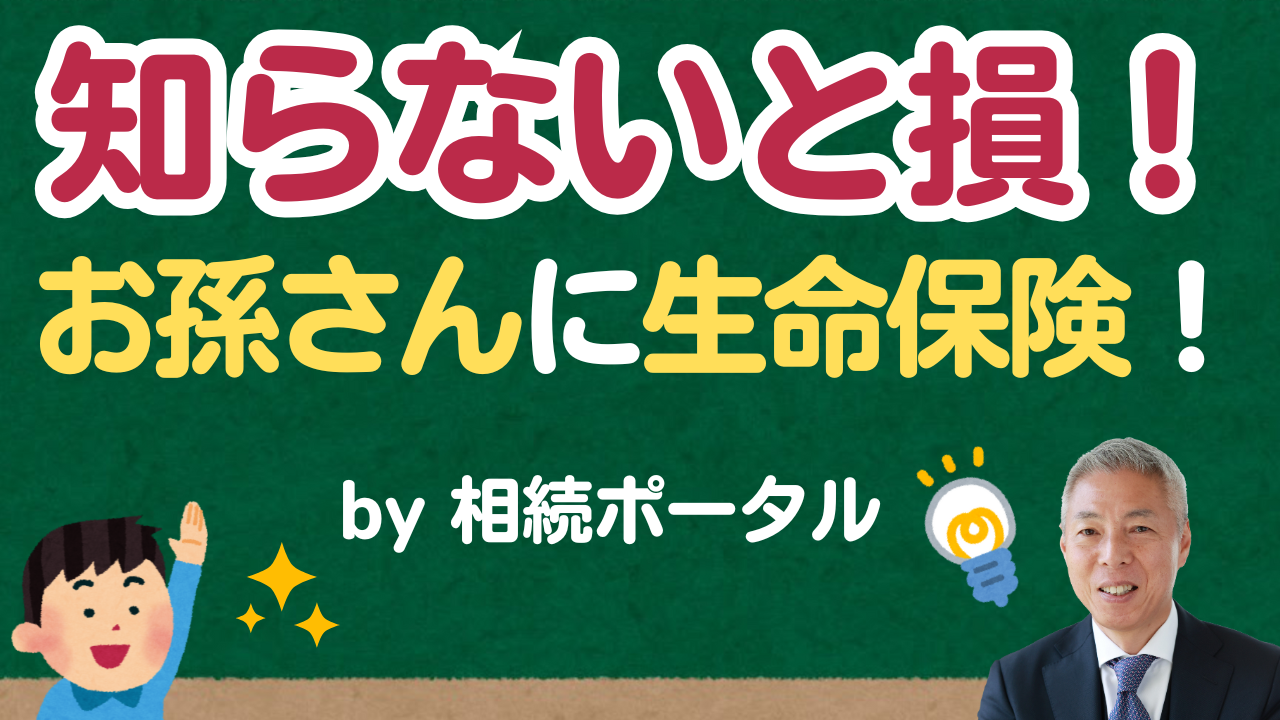
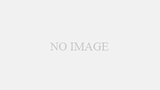
コメント