「うちは仲がいいから相続トラブルなんて無縁」——そう思っていませんか?
実は、そんな“安心感”こそが一番の落とし穴。この記事では、実際に家族関係が壊れてしまった相続トラブルの実話をもとに、「なぜ揉めるのか?」「どうすれば防げるのか?」をわかりやすく解説します。
平和な家庭が一転…遺言書のない相続の悲劇
ある日、長年家族を支えてきた父親が亡くなりました。特別に財産が多いわけでもなく、兄弟仲も良好。誰もが「うちは揉めるわけない」と思っていた家庭です。
しかし、問題は「遺言書がなかったこと」。
「父は自分に家を譲るつもりだったはず」「預金は兄が取りすぎだ」などと、それぞれの思いがぶつかり合い、話し合いは泥沼化。最終的には裁判にまで発展し、家族は絶縁状態になってしまいました。
このようなケースは、決して珍しくありません。むしろ、「自分たちには関係ない」と思っていた家庭ほど、準備不足でトラブルになりやすいのです。
相続が“争続”になる理由
相続トラブルの背景には、財産そのものよりも“感情”のもつれが深く関係しています。
- 「長男だけ介護をしていたのに、取り分が同じ?」
- 「遺産の分け方が不公平」
- 「話し合いができないまま相手が勝手に進めていた」
こうした不満が爆発し、冷静な話し合いができなくなるのが典型的なパターンです。
しかも相続には、法定相続分や遺留分といった法律のルールがあるため、「知らなかった」が致命的な争いの火種にもなります。
「うちは大丈夫」は通用しない
「兄弟仲がいいから」「財産が少ないから」と安心して準備を怠ると、逆に深刻なトラブルにつながります。
実は、小さな財産ほど「これしかないのに、なぜ自分の取り分が少ないのか」といった不満が生まれやすく、分け方に対する感情的な衝突も多発します。
さらに、相続の知識がなければ、生命保険が相続財産に含まれないことすら知らず、「ズルい」「不公平」と感じる人も少なくありません。
トラブルを防ぐカギは「遺言書」と「話し合い」
では、相続トラブルを未然に防ぐためには何が必要なのでしょうか?
最も効果的なのが「遺言書」の作成です。
自筆証書遺言や公正証書遺言といった方法がありますが、確実性や法的な効力を重視するなら、公正証書遺言がおすすめです。
また、遺言書だけでなく「エンディングノート」も感情的な対立を和らげる効果があります。法的な効力はありませんが、「自分の気持ち」を家族に伝える手段としては有効です。
さらに、相続に関しては税金・不動産・法律など多岐にわたる分野の知識が必要になるため、専門家(司法書士・税理士・弁護士など)への相談が非常に重要です。最近では、無料相談やオンラインでマッチングできるサービスも増えてきました。
相続の第一歩は“全体像”を知ること
いざ相続が発生すると、財産の棚卸し、相続人の確定、分け方の協議、名義変更など、多くの手続きが待っています。
しかも、相続には期限もあります。たとえば相続放棄には3か月以内というリミットがあるなど、「知っていれば防げた」失敗も少なくありません。
まずは、「相続ってどんな流れで進むのか?」という全体像を押さえ、法律の基本ルール(法定相続分・遺留分)を理解しておきましょう。
まとめ:備えることが“最後の家族思い”
相続の話は、「まだ早い」「縁起でもない」と避けがちです。しかし、それを先延ばしにした結果、かえって家族の絆が壊れてしまうケースは後を絶ちません。
相続は、家族にとって“最後の共同作業”とも言えます。
だからこそ、早めの準備と、冷静な話し合い、そして正しい知識が何よりも大切なのです。
📘もっと知りたい方へ
相続の無料相談サービスや遺言書作成サポート、初心者向けの相続ガイドブックなど、詳しい資料をご希望の方は、下記のリンクからチェックしてみてください。


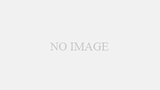
コメント